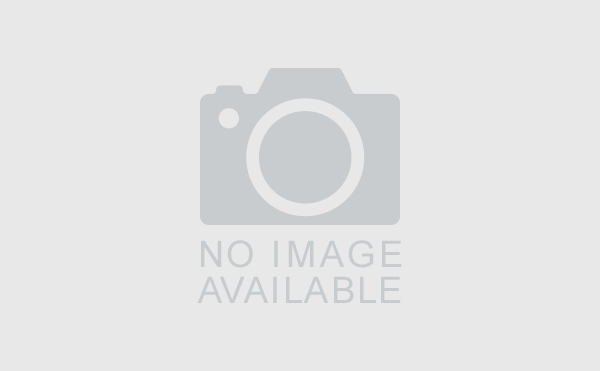読書
途中までしか読んでいないが、カストロの『食人の形而上学』という本を最近読んでいる。
内容は人類学とポスト構造主義の融合という感じで難解だが、自分の思想に通ずるところもあって面白い。
例えばジャガーにとっての人間の血はビールであるというように、非人間にも人間のパースペクティブがあるという主張が目を引く。
最近ルッキズムや親ガチャといった気分が悪くなる思想が流行っているが、人間であること、ひいては人間が遺伝子や脳の化学物質の乗り物であることってそこまで重要なのかと疑問に思う。
宇宙のあらゆる構成要素が潜在的に人間であるというカストロの主張は、一見受け入れ難いが、言いたいことはなんとなく分かる。
例えば洗濯機は確かに人間ではないが、人工物という形で自然に存在し、自然の中では人間と区別されない。
人間であることよりも人間らしくあることの方が重要だと思う。精神こそが人間を決定づけるからだ。
洗濯機にも人間らしさや精神があるというのは依然不自然だが、それは精神が無数にあると考えているからだ。
自分の精神だけを頼りに洗濯機を見たとき、それがそれまでの洗濯機と同一に見えなくなるときがある。
そういうときの精神の変化に気づくときは爽快な気持ちになる。こういう感じで自分の精神の形を知覚する見方を身に着ければ楽しいと思う。
就労継続支援A型事業所(株)Grow-UP利用者 N.R