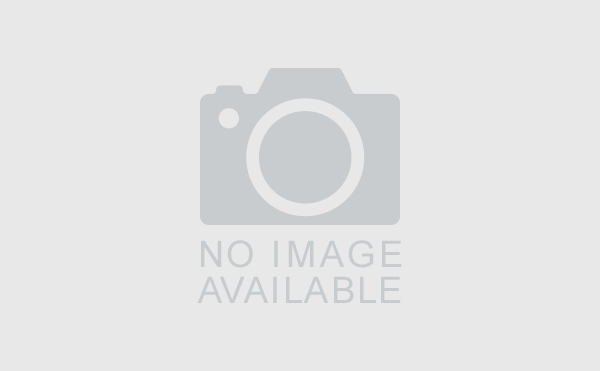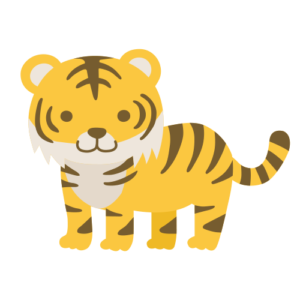春分の日
毎年3月20日頃に訪れる祝日「春分の日」は一年間で昼と夜の長さが同じになる日として知られていますが、毎年日にちに変動がある理由やその背景を知る人は少ないでしょう。
「春分」は太陽の動きをもとに一年間を24つに分けた「二十四分節」の一つ・立春からはじまる4つ目の節で、現在でもおこなわれている皇室の行事「春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)」からこの名が付きました(皇霊祭は歴代の天皇・皇族を祀られ、現在でも催されている宮中祭祀)。
では、なぜ「春分の日」は祝日だと定義されているのかは、古くから春分の日には「春季皇霊祭」、秋分の日には「秋季皇霊祭」という宮中祭祀が催されたことに由来します。
戦前の日本においてこの2つの祭祀はとくに重要視されてきたため、さまざまな変遷がありつつも1948年に「国民の祝日に関する法律」によって祝日に制定されました。
ちなみに同法律内で春分の日は「自然を称え、生物を慈しむ日」、秋分の日は「先祖を敬い、故人を偲ぶ日」と記載されています。
この頃には花や草木も萌え始め、春らしい陽気になるでしょう。今日は先日と比べて若干暖かさが出てき始めているため、このような気温が続けば4月ごろに桜が満開を迎えるでしょう。
4月はお花見にあつらえむきな月であるため、4月ぐらいになればどこか桜がきれいに見える場所に行ってみるのはいかがでしょうか。
就労継続支援A型事業所(株)Grow-up 利用者C.Y