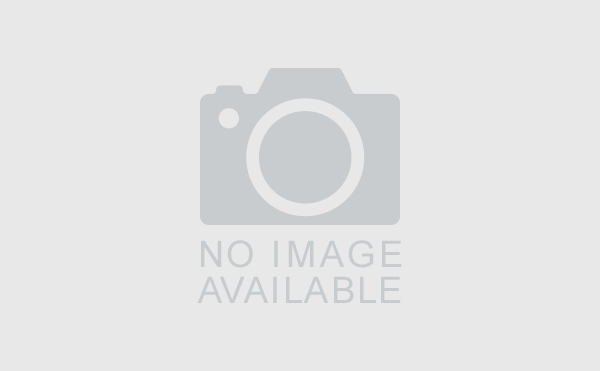お好み焼きのルーツ
お好み焼きのルーツは煎餅(せんびん)といい、小麦粉を水で溶いて平らに焼いただけの料理でした。
大昔、夏(か)の頃(新石器時代)から似たものが既に作られていたようで、陶ごうという煎餅を焼く調理器具が普及していた当時から庶民の食卓に普及していたようです。
そして戦後の飢餓の時代、にわかにクローズアップされた食べ物・子供達の間で人気のあった駄菓子屋の「一銭洋食」の上に申し訳程度の豚肉を乗せ、呼び名を「一銭洋食」から「お好み焼き」へと変更し、大人の食べ物として通用するものにしました。
このようにして新しい世界に踏み出した「お好み焼き」でしたが、その後広島市内にお好み焼き屋台や店が増え始めます。
当時の広島は工場が多く比較的鉄板を手に入れやすい環境でしたが、お好み焼きは空腹をしのぐ食べ物として街の片隅でほそぼそと焼かれていました。
広島県民にとってお好み焼きはソウルフードで、観光客にとってはご当地グルメとして愛されています。
私も今度広島へ旅行に行ったなら、お好み焼きを真っ先に堪能したいです。
就労継続支援A型事業所(株)Grow-up 利用者C.Y