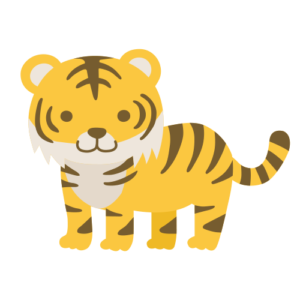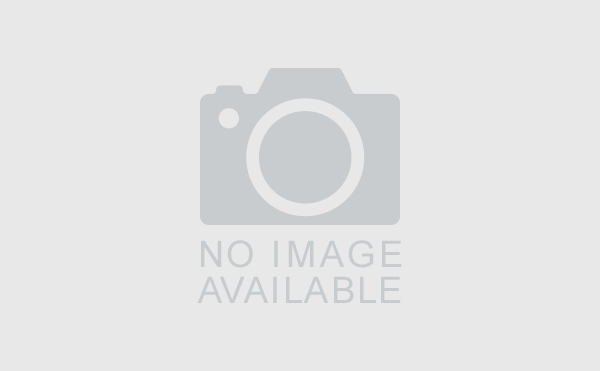救急の発祥地
9月9日は「救急の日」で、この日を含む1週間は「救急医療週間」として昭和57年から日本全国で毎年救急に関わる様々なアクティビティ・行事を実施し、人々に救急業務への理解と認識を深めてもらうために努めています。
その日にちなんで、今回は消防・救急が神奈川県横浜市で発祥したのか説明します。
1859年に開港した横浜は翌年外国人居留地が設立され、商品を火災で焼失することを一番恐れていた横浜に滞在する当時における海外の貿易商人達は防災の為、自主的に欧米から最新の機械を取り寄せ小規模な消防組織を結成しました。
1866年に起きた大火事『豚屋火事』が起こったその後、消防隊は強化され1864年には「居留地消防隊」と呼ばれるポンプ車を備えた日本初の組織が発足しました。
また、防火対策で隣接していた日本人街と外国人居留地は日本大通りを隔てて分断され、消防組織が作られると同時に横浜市には救急隊も設置されました。
そして1933年、篤志家という名家から救急自動車が寄贈され消防機関による救急業務が開始しました。
当時は自動車の普及によって交通事故の増加が社会問題となっており、特に負傷者の早期救護が重要であることから救急自動車が配置されました。
横浜は日本の有名な港町として知られますが、歴史的背景を知るとまた違った見方が見られます。
就労継続支援A型事業所(株)Grow-up 利用者C.Y